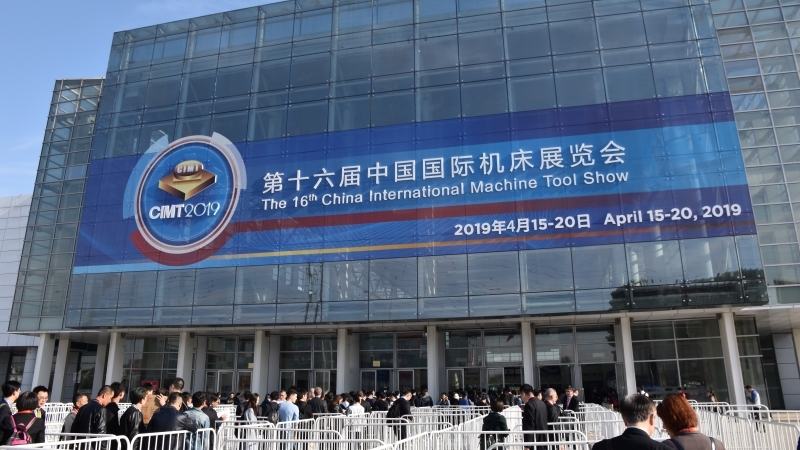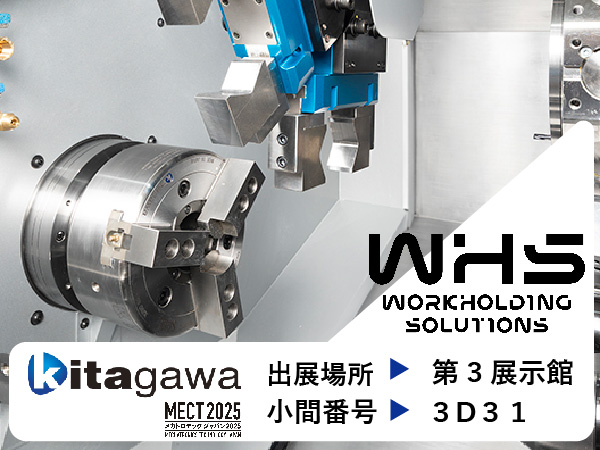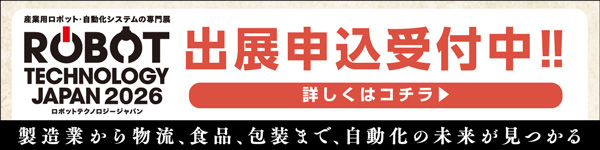[特集 国際ロボット展vol.3] ロボット事業を4倍規模に/川崎重工業 高木登 執行役員ロボットディビジョン長
物流ソリューションやデジタルプラットフォーム提案
――3月9日からiREXが始まります。
今年は海外来場者が見込めないこともあり、オンラインでも全ての情報が発信できるよう準備しています。展示テーマは大きく3つです。1つ目は先ほど申し上げた2つのキーワードに関わる部分です。医療分野の展示やリモート・ロボット・サービス・プラットフォーム、配送ロボットなどを展示します。
――3つ目の展示テーマをお願いします。
ロボットのデジタルプラットフォーム「ROBO CROSS(ロボクロス)」の提案です。今後の社会ではデータをいかに集めて有効利用し適切なサービスを継続的に提供するかが問われます。そこでロボットが社会全体のデジタル化の推進力となることを目指し、これまでになかった「価値」を提供します。例えば顧客向けには生産やメンテナンスの効率を上げるサービス、SIer向けにはシステム設計をしやすくするサービスなどの提案を考えています。
――日本の製造業と自動化の未来をどうみますか。
生産年齢人口が減りますので、人が従来やっていた仕事をいかにロボットにさせるかが課題です。しかし、ロボットが導入されていない分野は、そもそもロボット化が難しいから入っていないわけです。ですから、「完全なロボット化はできない」との認識を持ち、10人でやっていた作業を2人+ロボット5台でやる、といった発想が必要になります。また、既存の設備にロボットを導入しようとしても制約がたくさんあります。ロボット化を前提とし、設備をどう整えるかが重要です。例えば、箱の持ち手の形を統一する、手で横に引かねばならないドアに開閉ボタンを付ける、といったことをするだけで各段にロボットを導入しやすくなります。そうした環境を整えるにはどうすればいいかについて、設備メーカーなどと検討を進めています。
(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角 秀)
高木 登(たかぎ・のぼる)
1985年京都大学工学研究科修士課程修了。2001年川崎重工業入社、精密機械カンパニーロボットビジネスセンターFAシステム部長などを歴任。14年Kawasaki Robotics GmbH出向、15年Kawasaki Robotic (UK) Ltd.出向、19年精密機械・ロボットカンパニーロボットビジネスセンターFAソリューション第一総括部長、20年から現職。香川県出身。1960年生まれの61歳。