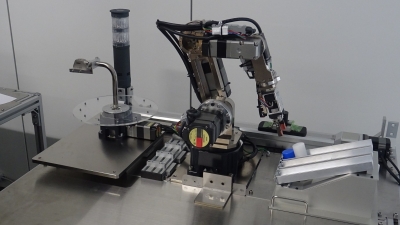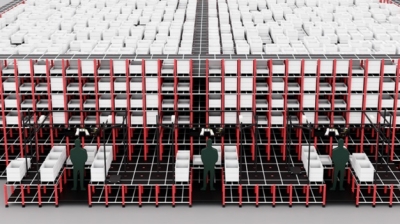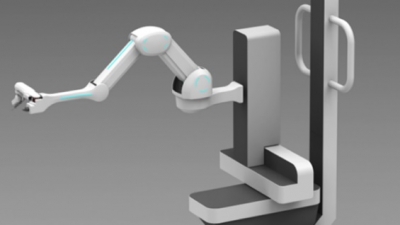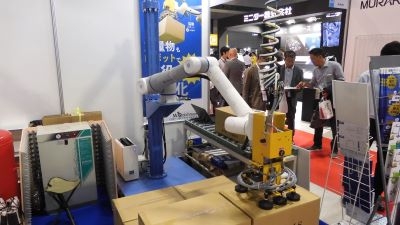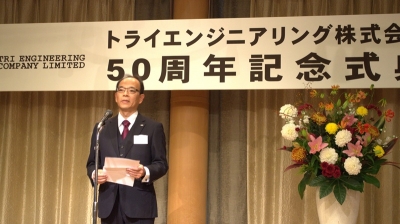「1日工場診断」を開始、3つのサービスで最適な自動化を/ロボカル
【ショートインタビュー】ロボットの普及を阻む課題を解決したい
ロボカル芦川泰彰社長2021年にロボカルを創業した芦川泰彰社長。以前は別業界で事業をしていたという。なぜロボット業界で起業し、現在のような事業を始めたのか。その背景や考え方を聞いた。――――――――――――――――――――ロボカルを創業した経緯を教えてください。私は元々、IT業界の起業家でした。ロボカルを創業する以前は、交通事故にあった際の通院先を提案するウェブサービス事業を運営していました。「交通事故にあってしまったけれど、どうすればよいか分からない」という困りごとを解決するもので、現在でも多くの方々にご利用いただいています。その事業が軌道に乗ったため、株式の過半を譲って社長も退任し、次に手掛ける事業を探している中で知ったのがロボット産業でした。マーケティング事業部の矢部秀一ディレクターとは高校時代からの友人で、彼は当時、大手ロボットメーカーの社員でした。彼にロボット業界の話を聞く中で、その潜在的な可能性と課題に気が付きました。――その課題とは?ユーザーがロボットを導入したいと思っても、必要な情報や知識がないことです。どの工程にどのようなロボットを導入すればよいのか、どのSIerに依頼するのが最適か、ユーザーには分かりません。売り手と買い手で持っている情報に格差がある、この「情報の非対称性」がロボットの普及を阻んでいます。この問題を解決できれば、ロボットの市場は飛躍的に拡大させられると見込んでいます。――創業当初から現在のビジネスモデルですか?当初はロボット導入を考える企業とSIerをマッチングする事業を考えていました。交通事故の被害者と通院先の病院をマッチングするこれまでの事業の応用ですね。しかし、ロボット導入の場合は「紹介して終わり」ではなく、ワンストップ対応を求める顧客ニーズが高かった。そこで、SIerと連携しながら、自社で受注して責任を持ってロボットシステムの構築までできる体制を整えました。――「情報の格差」に着目した点が、元IT(情報技術)業界の起業家らしいですね。ロボカルのメンバーは、ロボットSIerとして豊富な経験を持つ日比野学主席コンサルタントや、元大手ロボットメーカーの矢部秀一ディレクターなど、ロボットに精通した人材をそろえています。しかし私自身は、IT業界の出身です。ロボット業界とIT業界では慣習なども違いますが、他業界の出身者だからこそ変革できることもあると思います。人工知能の開発など、技術面で新たなことを提案するベンチャー企業は数多くあります。しかしロボカルは、ビジネスモデルの側面から業界を変革したい。幸いパートナー企業など協力者にも恵まれ、順調に実績を伸ばしています。――どのような企業からの受注や引き合いが多いですか?お客さまは非常に多様です。大手企業ももちろんいますが、ロボットを初めて導入する中小企業や三品産業(食品、医薬品、化粧品)も多いですね。珍しいところではウナギ屋兼ウナギ卸売り問屋の焼き工程にもロボットを導入しました。まだあまり導入が進んでいない中小企業や三品産業も含め、さまざまな製造現場にロボットが普及すれば、日本のものづくりはもっと強くなると確信しています。また先ほどのような課題は海外でも同様であり、海外展開も視野に入れています。ロボカルの理念に共感してくれるパートナーやスタッフを積極的に増やしながら、ロボットの普及や製造業の発展に貢献できればと思っています。(聞き手・構成ロボットダイジェスト編集デスク曽根勇也)