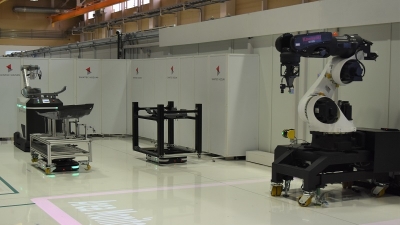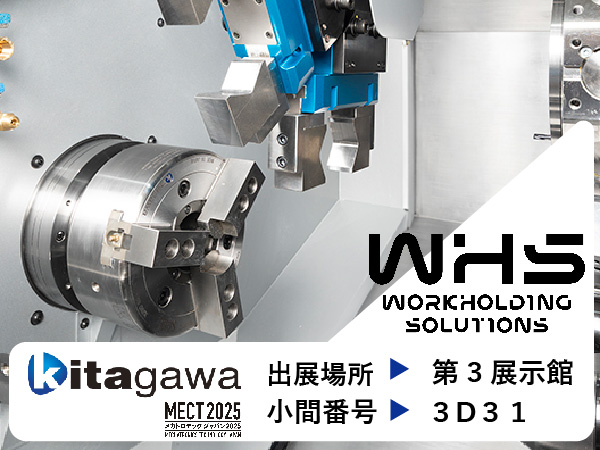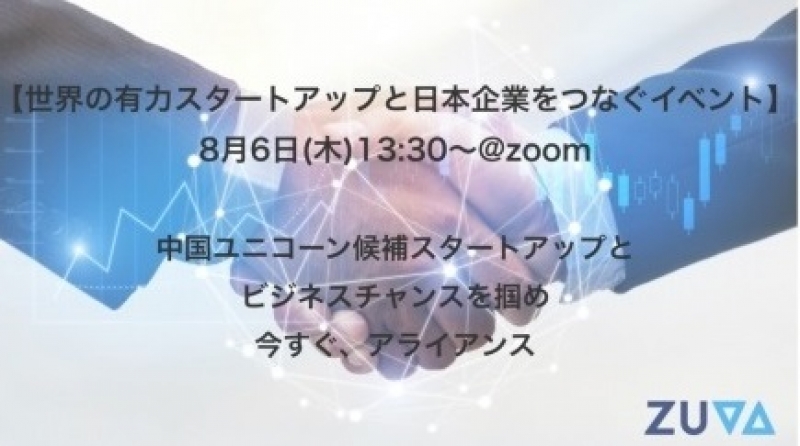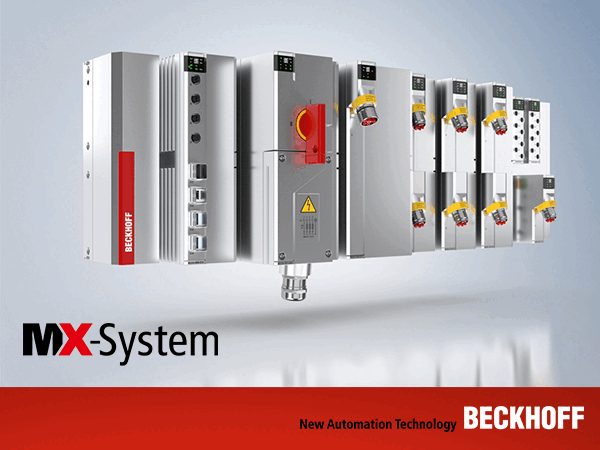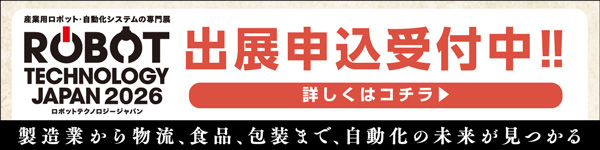大手ロボットメーカー幹部が未来を語る【後編】/RTJ2022「スペシャルセッション」
自動化のアプローチは一層多様化
小川昌寛氏 ロボットのニーズや需要はさまざまな産業に広がっています。ところが、われわれメーカー側は今まで、それに応えられていませんでした。今後対応できたものから順に、活用領域は広がっていくでしょう。ロボットによる自動化はサステナブルな社会を作るために必要ですから、特定の産業や作業内容ではなく、全ての生産活動が対象であるべきです。
あらゆる生産活動の中でも、決められたことを繰り返す生産性の追求には大いに貢献できたと満足していますが、変化の多い不確かな状況ではロボットは使えないとの認識が根強いです。変動要素に対応するロボットの開発や自動化を追求し、できたものから順にロボットの新たな活用領域になると思います。
また、今まで成果を出してきた大量生産の分野でも、変種変量生産の大きな波が来ており、今まで通りの自動化の考え方では、レスポンスや多様性への対応が難しくなっています。これも最近の課題です。
稲葉清典氏 自動化のアプローチの仕方から、成長分野についてお話しします。
人手が主体だった生産現場を自動化する場合、大きく分けて二つのアプローチがあると思います。一つは、従来の作り方を完全に変えて自動化システムを導入するケース。もう一つは、従来の作り方に後付けでロボットを導入するケースです。最近は後者のケースが急速に増えています。
また自動化システムの中でロボットは一つの要素でしかなく、ソリューションを提供するのは従来、SIerや機械メーカー、商社が担ってきました。最近では、簡単なロボットが出てきたことで、ユーザー自身が好きな標準品を集めて簡単なシステムを作り上げるケースが増えてきたと感じます。好きなパソコンとプリンターをつなげてシステムを作るのと同じような感覚です。
――活用領域を広げるには、民間だけでは難しいこともあると思います。皆さんの話を聞いて、大星室長はどう思われますか?
大星光弘氏 せっかくロボットを導入したものの、うまく活用できなかった方は多くいます。われわれ経済産業省は、ロボットの活用領域を広げるため、受け入れる側も一緒に考える『ロボットフレンドリー』という取り組みを進めています。例えば食品であれば、ロボットが持ちやすい容器に入れてもらうなど、互いに歩み寄れば、ビジネスになりやすいのではないかと思います。