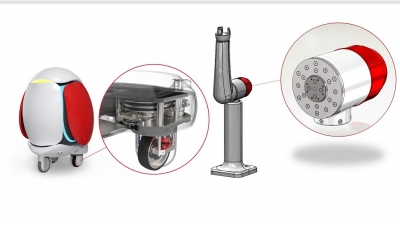[2023国際ロボット展リポートvol.13]協働ロボットの普及はまだまだ“初期段階”/ユニバーサルロボット ステイシー・モーザーCCO
人手不足の日本には協働ロボットが足りない
――URにとっての日本市場とは?
日本は、最も重要な協働ロボットの市場です。米国や欧州、中国なども同様ですが、日本は人材不足に直面しています。5年後には700万人分の人手が不足するとも言われています。労働人口は減少し、また製造業を希望する若者も減少傾向にあります。日本は産業用ロボットの新規導入台数が非常に多い国で、年間で全世界50万台の約1割に当たる約5万台が導入されていますが、不足する人手を考えるとそれだけでは十分ではありません。
――協働ロボットの導入を加速させる必要がある?
日本では10年前から、URの協働ロボットの導入が始まりました。この10年間で市場を広げ、製品ラインアップも拡大してきましたが、いまはまだ「初期段階」だと思っています。われわれのロボットは人手作業の代替やサポートに主眼を置いており、現在人手で行っている作業の置き換えには協働ロボットが最適です。人手不足の日本にはロボット、特に協働ロボットが普及拡大する余地がまだまだあります。日本でも今後の市場成長率は、産業用ロボット全体よりも協働ロボットの方が間違いなく高くなるでしょう。
――今年の7月には、日本でもプライベートショーを開催されました。
愛知県で開催し、想定を上回る900人以上の来場がありました。日本企業の協働ロボットへの関心の高さを感じることができました。実際に導入したエンドユーザーに講演してもらい、どのように導入したのか、どのように安全確保をしたのかなど話してもらうことで、聴講者の導入に向けた心理的なハードルを下げることができたように思います。
――日本市場での課題は?
認知度をもっと高め、教育を広める必要があります。日本には13社の販売パートナーがおり、10カ所のUR認定トレーニングセンターがあります。トレーニングセンターでは日々研修などを行っていますが、日本はまだまだ海外と比べ、協働ロボットの研修や教育が広がっていません。日本の労働人口は今後ますます減少し、自動化の重要性は高まっていきます。日本が先進的な製造業の国として今後も成長していくためには、協働ロボットが欠かせません。協働ロボットなら中小企業の狭い現場にも導入しやすく、高齢者のスキルをロボットに覚え込ませることでスキルの継承もできます。日本の現場にとても適した製品で、無料のオンライントレーニングなどもありますので、ぜひ多くの方に使い方の教育を受けてもらい、簡単に使えることを知ってもらえればと思います。
(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角秀)
Stacey Moser(ステイシー・モーザー)
米国テクトロニクスのグローバルセールスおよびオペレーション担当バイスプレジデント、米国GE DigitalのCCOなどを経て2023年6月より現職。米国インディアナ州パーデュー大学出身。
同じ企業の記事
>>導入検討の最初の一歩が“超”手軽に/ユニバーサルロボット
>>ウェビナーで、先の読めない時代に必要な柔軟性をアピール/ユニバーサルロボット
>>出荷台数2万5000台を記念して金色のロボ贈呈/ユニバーサルロボット
>>協働ロボメーカーが日本支店を移転/ユニバーサルロボット
>>インドでBFWと提携/ユニバーサルロボット
>>難易度の高いパイプ溶接システムの実現に貢献/ユニバーサルロボット
>>SMCの真空グリッパーをUR+に認証/ユニバーサルロボット
>>林業の苗木生産に協働ロボが採用/ユニバーサルロボット
>>組み込み仕様の協働ロボットを発売/ユニバーサルロボット
>>ウェブ上で協働ロボのセミナーを開催/ユニバーサルロボット
>>9日からウェブ展開催、パートナー企業22社も出展/ユニバーサルロボット
>>全国5都市に認定トレーニングセンター開設/ユニバーサルロボット
>>[人事]新社長にテラダインのグレゴリー・スミス氏/ユニバーサルロボット
>>世界で累計販売台数5万台を達成/ユニバーサルロボット
>>協働ロボットのバーチャル展開催、2月19日まで/ユニバーサルロボット
>>新社長にキム・ポヴルセン氏/ユニバーサルロボット
>>協働ロボットのオンライン展を開催/ユニバーサルロボット
>>UR10eの可搬質量を25%向上/ユニバーサルロボット
>>板金工場の溶接工程に協働ロボットが採用/ユニバーサルロボット
>>愛同工業の自動車部品工場に協働ロボ導入/ユニバーサルロボット
>>過去最高の売上高を達成/ユニバーサルロボット
>>日東工器の電動ドライバーをUR+製品として認証/ユニバーサルロボット
>>ナベルHDのロボットカバーをUR+製品として認証/ユニバーサルロボット
>>認定トレーニングセンターを拡充/ユニバーサルロボット
>>パートナー27社とオンライン展開催/ユニバーサルロボット
>>稼働モニタリングなどユーザー向け新サービスを開始/ユニバーサルロボット
>>四国、中部のSIerがURの認定取得/ユニバーサルロボット
>>パートナー企業35社とオンライン展、9月12日から/ユニバーサルロボット
>>三菱電機と共に協働ロボットの稼働監視ウェビナーを開催/ユニバーサルロボット
>>ハイオスの電動ドライバーがUR+認証取得/ユニバーサルロボット
>>日本初のフェア開催、協働ロボの市場広げる手助けに/ユニバーサルロボット
>>「URアカデミー」の受講者数が全世界で20万人突破/ユニバーサルロボット
>>30kg可搬の協働ロボット発売! 高可搬だがコンパクトで軽量/ユニバーサルロボット
>>ユーザーのロボット活用を支援するプログラムを開始/ユニバーサルロボット
>>エアグリッパーとTIG溶接パッケージをUR+に認証/ユニバーサルロボット
>>協働ロボットフェアで周辺機器やソリューションが一堂に/ユニバーサルロボット
>>3社をシステムインテグレーターとして認定/ユニバーサルロボット
>>国内のサービス体制を強化、サービスハブや部品倉庫を開設/ユニバーサルロボット
>>UR史上最速の新型協働ロボットを発売/ユニバーサルロボット
>>協働ロボットでも速い! 新製品や新ソフトを国内初披露/ユニバーサルロボット
>>協働ロボのフェア開催、自動化の次の一手を提案/ユニバーサルロボット
>>8kg可搬のロングリーチ仕様を発売/ユニバーサルロボット