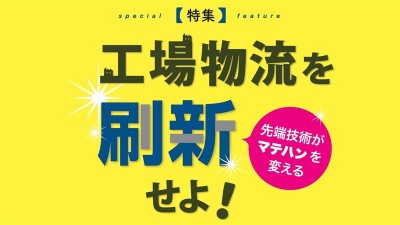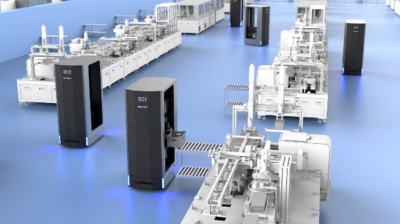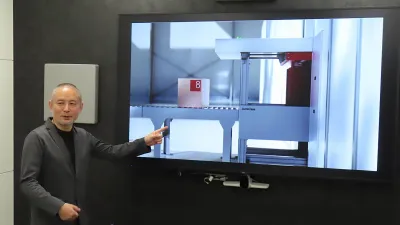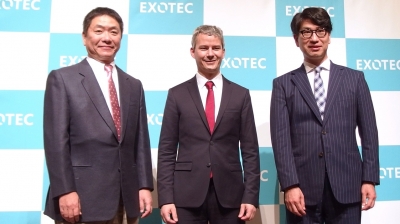[特集 工場物流を刷新せよ!vol.2]「革新の分岐点」作り続ける、ニッチで光る技術を/村田機械 村田大介 社長
「労をいとわず、失敗を恐れず、失敗から学ぶ」
――村田機械におけるL&A事業の位置づけとは。
わが社は創業88年で、もともとは繊維機械メーカーとして始まりました。それに物流システムをはじめ「工作機械」、「情報機器」、そして先に触れた半導体の「クリーンFA」が加わって、現在は5分野で事業展開しています。L&A事業部の素地となる物流機器には1962年に参入しています。基本的に機械メーカーなのですが、機械そのものというより、機械とエンジニアリングソリューションの両方を売る企業であるところが特徴です。また、メーカーがお客さまである事業が多い中で、L&Aは必ずしもそうではないのがユニークな所です。従来から流通業は大きなターゲットですし、今後は病院など医療関連での取引も増やしたいと考えています。
――5つの異なる分野で事業展開をしていてシナジー(相乗効果)はありますか。
目に見えるようなはっきりとした例は少ないものの、『多分野でやっていて良かった』とはずっと感じています。例えば、オフィス向けのファクスやコピーを取り扱う情報機器事業では、それらの製品分野が今後伸びる可能性は小さいかもしれません。しかし、そこで培った情報通信の技術は他の事業分野で大いに生かせます。情報機器に限らず、ある事業部から今後さらに忙しくなりそうな別の事業部へ異動してもらうなど、人材面でのシナジーがまずあります。元々の所属ではあまりうまくいかなかった人が、次の部署で花開くこともあります。また、シートメタル加工機と材料・完成品の供給・保管システムを組み合わせるなど、マテハン技術と他の機械を組み合わせる提案も増えています。いろんな事業をやっていることによる中間領域のメリットを感じるところです。
――経営者として重視していることは。
ちょうど20年前社長に就任した時に自らに課した、「労をいとわず、失敗を恐れず、失敗から学ぶ」姿勢を今でも大切にしています。産業機械は基本的に安定したビジネスです。お客さまとの関係性も長くて深いし、事業が大きくなるとそれを支えるライン業務の充実により多くの人やお金を回したくなります。放っておくと新しいことへのチャレンジが疎かになってしまうんですね。でも、われわれは機械メーカーですから、ニッチ市場でキラリと光る企業であり続けるには技術開発が大事です。しかも5事業もやっているわけですから、いたずらに規模を追わずオンリーワンをたくさんもっている会社を目指しています。
――なるほど。
実はこの4月に新たに企業スローガン「革新の分岐点」を制定しました。88年の歴史をひも解くと、結構いろんな場面で業界の分岐点となるソリューションを提供してきたことが分かります。近年は、先ほどお話しした新しい顧客層との接点もできてきたので、お役立ちできるような新しい機械もどんどん作れると感じています。技術開発で社会を豊かにする「革新の分岐点」を作り続けるのが、今後もわが社の使命です。
(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角 秀)
村田 大介(むらた・だいすけ)
1984年一橋大学経済学部卒業、京セラ入社。87年村田機械入社、米ムラタ・ビジネス・システムズ出向。90年スタンフォード大学大学院経営学専攻修了、MBA。91年村田機械情報機器事業部業務部長、94年取締役、97年常務、2000年専務、03年から現職。1961年生まれ、京都府出身の61歳。
※本特集は「月刊生産財マーケティング」とのコラボレーション企画であり、同誌でもこの記事をお読みいただけます。
vol.2 「革新の分岐点」作り続ける、ニッチで光る技術を/村田機械 村田大介 社長
vol.3 マテハンのものづくりから運用提案まで、総合的なSI力に優位性/村田機械犬山事業所(6月5日に公開予定)
vol.4 ワーク着脱から工場物流まで、変種変量生産の自動化に威力/DMG森精機(6月6日に公開予定)
vol.5 物流革新で生産性15%増、効率以外の利点も/オカムラ・ファナックパートロニクス(6月7日に公開予定)
vol.6 配膳ロボットを工場に/三機・大野精工(6月8日に公開予定)
vol.7 一巡して一段高いステージへ/日本物流システム機器協会下代博 会長(6月9日に公開予定)
vol.8-① 現場の省人化・省力化を後押し、各社の一押し製品(6月12日に公開予定)
vol.8-② 現場の省人化・省力化を後押し、各社の一押し製品(6月13日に公開予定)
vol.8-③ 現場の省人化・省力化を後押し、各社の一押し製品(6月14日に公開予定)