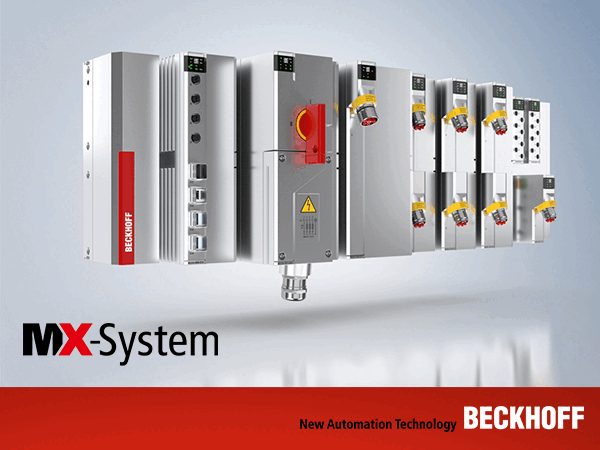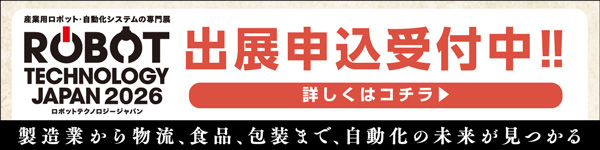低コスト、簡単立ち上げの自動化を/ファナック 山口賢治 社長兼CEO
目指すべきもう一つの方向性
――協働ロボットも導入しましたね。
今年4月の時点で、全社で4600台のロボットが稼働していますが、「緑色」の協働ロボット「CRシリーズ」はそのうち40台あり、さらに20台を追加で導入します。6月に発売した「白色」の協働ロボット「CRXシリーズ」は、今は需要があって顧客の方に回すだけで手一杯ですが、これから使いたいですね。
――どの工程に採用しましたか?
ロボマシンの組み立て工程が多いです。小型切削加工機「ロボドリル」の主軸周りや、電動射出成形機「ロボショット」のボールねじ周りのユニットの組み立てなどに使っています。従来のレイアウトを大きく変更せずに、そのまま人手の作業を置き換えられるのが協働ロボットの利点で、生産現場にまず1台、また1台と導入していきました。まだ稼働台数は少ないですが、徐々に成果が出始めたと感じています。
――具体的な導入成果は。
サーボアンプの組み立て工程で、従来の黄色のロボットを15台使った自動化システムがあったのですが、それを1人の作業者と5台の協働ロボットで構成されたシステムに置き換えました。設備投資額で従来比の50%、設置スペースで70%削減できました。最初は協働ロボット3台による組み立てのみの自動化でしたが、後から搬送など前後工程の自動化に2台追加しました。段階的に追加できるのも協働ロボットのいいところです。
――投資額もスペースも大幅減です。
私も初めて見た時は「すごいな」と驚きました。わが社はこれまで、黄色のロボットを使った手の込んだ自動化システムを構築してきました。こうしたシステムはピークに応じた能力設計をする必要がありますが、需要変動が大きいほどシステムが稼働しない時間も増え、償却負担が重くなります。従来型のシステムに加えて、低コストで簡単に立ち上げられる自動化システムも、目指すべきもう一つの方向性として追求します。事例は少ないですが、この考え方は他の工程にも水平展開できると期待しています。
――IoT基盤のフィールドシステムも自社工場に導入しました。
わが社では4600台のロボットに加え、自社のCNC装置を搭載した工作機械が1000台稼働しています。センサーなども含めると全部で約4000の機械装置類をフィールドシステムにつないでいます。フィールドシステムを使えば、工場内にあるさまざまな設備を同じ基準で可視化できます。生産技術の担当者がフィールドシステムを使い、可視化されたデータを集めて分析し、仮説を立てて検証し、改善につなげています。仮説検証のサイクルを個人単位で簡単に、そして高速で回せる体制を社内に構築できたのは大きなメリットです。
――アフターコロナの時代の工場運営のあり方はどう変わるでしょうか?
わが社の工場ではコロナ禍以前から進めている自動化やロボット化、IoT化を加速します。工場は現地、現物、現実の「三現主義」が中心ですし、現場には人も必要です。ただ、自動化対応はさらに加速し、管理系の従業員のリモートワークや設備のリモートメンテナンスも進むでしょう。
(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角秀)
山口賢治(やまぐち・けんじ)
1993年東京大学大学院修士課程修了、ファナック入社。2000年ロボット研究所一部一課長、2003年MT本部長、07年本社工場長、08年工場総統括、専務、12年副社長、16年社長兼最高執行責任者(COO)、FA事業本部長、19年4月社長兼最高経営責任者(CEO)就任。福島県出身。1968年生まれの52歳。