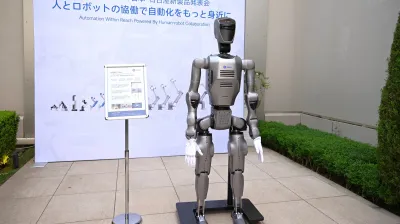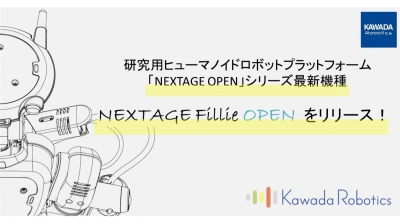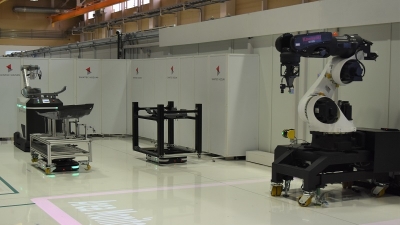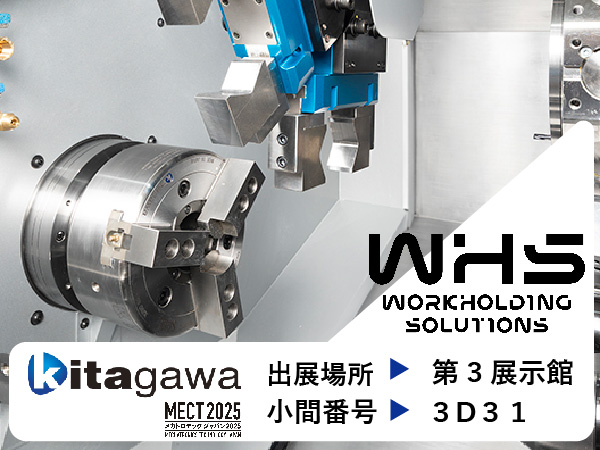「仕事は楽しんでやるもの」、産ロボから総合ロボメーカーへ /川崎重工業 高木登ロボットディビジョン長
熟練技能者の動きを継承
――他にも事例はありますか?
遠隔操縦システムの「Successor(サクセサー)」があります。コミュニケーターと呼ばれる装置を使ってロボットを離れた場所から操縦する技術です。サクセサーとは英語で「後継者」を意味します。そもそもは熟練技能者の動きを遠隔操縦でロボットに継承し、ロボットから新人作業者に伝承するために開発した技術でした。ところが、遠隔操縦機能に関して、いわゆる3K(キツい、汚い、危険)と呼ばれる職場からのお声掛けを多数いただきました。作業現場にロボットを置いて、人は環境のいい離れた場所から操作するわけです。
――具体的にはどういった用途があるのでしょうか。
例えば、大型部品の塗装やグラインダー掛け、高圧洗浄などがあります。建築業界ですと、高所作業、天井張り、耐火剤の吹き付け、床シート張りなどにも使われます。こうした職場は常に後継者不足、人手不足で悩まれていますから。
――今後のロボット市場をどう見通しますか。
とにかく伸びるでしょう。労働人口が下降傾向にあるのは各種データを見れば明らかです。また国際ロボット連盟が発表している製造業従事者1万人当たりのロボット導入率の国際比較を見ると、2018年の世界トップはシンガポールの831台です。世界で最も積極的にロボットを導入している国でも対労働者比率は8%に過ぎません。日本は世界第四位でたった3%です。製造業の全ての仕事がロボットに置き換わることはありえませんが、置き換えの余地が大きいことは容易に想像できます。しかし、現段階ですでにロボットが多数導入されている市場だけを見ていても伸びはそれほど大きくないでしょう。先ほど申し上げた「今まで使われなかった業界にロボットを」とわれわれが言っている意味はここにあります。
――しかし新市場、新機軸を創出するのは大変なことです。
手始めに10月1日付で商品企画部を新設しました。さまざまなアイデアを形にし、顧客に見ていただくための部門です。私は今年ロボットディビジョン長に就任したのですが、まずやったのが組織変更です。新しいことをできるようにするには“箱”というか、組織体制も大事と考えています。
――詳しくお願いします。
今までのわが社のロボット事業は、市場に新しい何かを投入するというより、顧客から『こんなものを作って欲しい』との話を受け、既存の技術力を駆使して応えることが多かったんです。その殻を破ったのがデュアロやサクセサーでした。こうした全く新しい製品や技術は、当初に想定した以外の市場のニーズにもマッチし、評判になりえます。私のモットーは「仕事は楽しんでやるもの」です。そうでなければいい結果は生まれません。そこで、社員一人一人がもっと自由に、もっと好きなことにチャレンジできる風土にしたいと思い、組織を少し変えました。「自由に提案していいよ」「好きなことしていいよ」とただ上から言われるだけでは、人はなかなか動けませんからね。
(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角秀)
高木登(たかぎ・のぼる)
1985年京都大学工学研究科修士課程修了。2001年川崎重工業入社、精密機械カンパニーロボットビジネスセンターFAシステム部長などを歴任。14年Kawasaki Robotics GmbH、兼Kawasaki Robotic (UK) Ltd.出向、19年精密機械・ロボットカンパニーロボットビジネスセンターFAソリューション第一総括部長、20年4月執行役員精密機械・ロボットカンパニーロボットディビジョン長。香川県出身。1960年生まれの59歳。