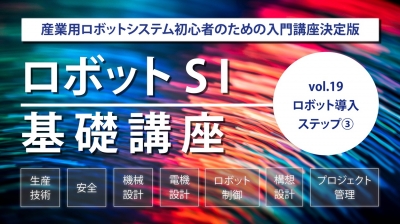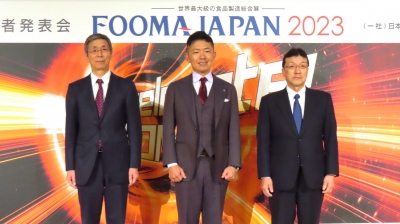“身の丈の自動化”が普及の鍵/自動化推進協会松元明弘会長
メカとデジタルを適材適所
――最近はセンサーを多数組み込んだ自動化システムも多いようです。
次世代の自動化にはモノのインターネット(IoT)などのデジタル技術も不可欠です。しかし、それだけでは不十分であり、からくりを含めたメカ技術と、IoTなどのデジタル技術を適材適所でうまく組み合わせたものが、今の時代に求められる価値ある自動化システムではないでしょうか。
「欲張りすぎない」が重要
――自社に自動化システムを導入したい場合、気を付けるべきことは?
これからの自動化で大切なのは「欲張りすぎないこと」。自動車産業などではほとんど人がいない完全自動化工場もありますが中小企業ではそれをまねるのは難しい。IoTでは「身の丈IoT」という言葉が最近使われますが、それと同じで身の丈に合った自動化を心掛けるべきです。まずは「自動化しやすいところだけやってみる」で良いのです。
――その他には?
失敗事例についても知っておいた方が良いでしょう。本や事例報告会では成功事例しか知ることができませんが、自動化にうまくいった企業でもそれまでには試行錯誤の段階でつまずいたり、諦めた部分があるはずです。
――そういった情報を知るにはどうすれば?
その企業に行って直接聞くしかありません。2018年に、埼玉県を中心に展開する武蔵野銀行と埼玉にキャンパスを持つ東洋大学が協力し、県内の中小製造業向けの勉強会「デジタル・エンジニアリング・アカデミー」を発足しました。自動化技術などを学ぶこのアカデミーでは座学だけでなく、身の丈での自動化に成功した工場の見学会なども実施したい。こうした地元企業を巻き込んだ取り組みが全国各地で展開されれば、中小を含めた多くの企業に役立つ身の丈の自動化が普及すると考えています。
(聞き手・構成 曽根勇也)
松元明弘(まつもと・あきひろ)
1983年東京大学大学院工学系研究科修了。東洋大学講師、助教授などを経て2004年から教授。09年に自動化推進協会の会長の就任。工学博士。鹿児島県出身の60歳。
※この記事は「月刊生産財マーケティング」2019年1月号特集「2019年どう攻める」に掲載したインタビューを再編集したものです。